私
たち家族はこの島に移り住んで足掛け13年になる。
我が家を訪れる人たちは大概、どうしてこの島で暮そう
と思ったのですかと尋ねる。彼らが知りたいのは、ごま
んとある島の中で何故口永良部島なのか、どんな動機が
あって都市暮しを捨てて島暮しなのか、であろう。
私は田舎暮しを企て地図をよく眺めはしたが、ついぞ島なるも
のは思いつきもしなかった。北海道を手初めにあちこち
見て廻リ、鹿児島へ来て海に突き当った。そこでやっと
島というものがあると気付いた。
さ
て地図を開いて、吐喝喇 ( トカラ ) 列島が一等好ましく思えた。
あちこち田舎なるものを見て私は全くうんざりしていた。
私は何を求めていたのだろう。とにかくどんづまりに行
きたかった。そこでじっとしていたかった。
私独りなら
都市の中でも自ら辺地を作りそこに竜っていただろうが、
私には妻子があった。都市に暮していてもとどのつまり
はルンペン暮し、何処に暮そうとも不安など芥子の粒ほ
ども無かった。
吐喝喇列島の諏訪之瀬島にヒッピーさんたちが住んで
いると聞かされた。私はヒッピーとは如何なるものかよ
く知らなかった。
口永良部島に住んで何人かの自称ヒッ
ピーさんがやって来たが、妙な手合いもいるが私には大
概の人たちよりはまともに見えた。
しかし私は群れるの
を好まない。とにかく諏訪之瀬島へ行ってどんな暮らし振
りか見てみよう。
十島丸というフェリーに乗るのだが、出航したばかり
で一週間先でないと戻って来ないという。屋久島へは毎
日出ているとの事で、11月初句だが暑いくらいの穏や
かな海を屋久島へ向った。
屋久島は初め小さく見え出し
たが近づくにつれて大きさを増し、峨々たる山並を連ら
ね、黒々とした樹々に覆われ呆れる程大きな島であった。
着いた。訳も分からず歩き出した。
広いアスファルト道
路、ブッ飛ばす車、土産物屋、1キロも歩いただろうか
ボーリング場があった。そこで私は廻れ石をして桟橋へ
戻ることにした。
私の住む処ではない。
乗
って来たフェリーの手前に、船体の下半分が朱色の
小さな船が停っていた。後で知ったのだが50トンの船
で太陽丸という。口永良部←→島間と表示してある。船
員に尋ねると今から口永良部へ行くという。
私は乗り物に弱い。
小学生の頃遠足が憂鬱の種であった。歩けばよ
いのにバスに乗る。一日中だ。皆ワイワイガヤガヤキョ
ロキョロ、チューインガムとキャラメルで口は動きっぱ
なしだ。
船室に入ると油とペンキの臭いで気分が悪くな
るので船尾に積んである荷物の横に腰掛ける。峨々たる
屋久島を左手に、太陽丸はそれこそトロトロと進む。エ
ンジンはボンボンと騒がしく、この船はどんな凪の日で
も揺れるに違いない。
1時間も走っただろうか、前方は操舵室で遮られ動け
ば気分が悪くなるので分からなかったが、右手に島影が
見え出した。まるっきり無人島みたいだ。
近づくにつれ
てその感は増々強くなった。何か古老のインディアンが
海に浮かんでいるようで、不思議に懐かしい気がした。
島を覆う緑は歩けばフカフカと気持の良い絨毯のよう
で、山頂は岩肌を見せている。私はこの島が火山島であ
ることを知った。
私
たちは当時東京国立市に住んでいた。
妻と長女長男
の四人暮しで妻は次女を懐妊していた。長女のぬい子は
三歳を過ぎて活発に動き廻り、私たちが住む露地裏長屋
から大して交通量は無いとはいえ、通りに飛び出すのを
ヒヤヒヤしながら暮していた。長屋の横手には小さな公
園があるのだが、そこは安心して子供を遊ばせておける
ような代物ではなかった。
すぐ近くに一橋大学があって
その中でやっと安心して子供を遊ばせることが出来た。
大きな大学ではないが、構内のあまり手人れされていな
い樹木やグラウンドは私たちにとってホッと息のつける
憩いの場であった。
大学の縁周りには太きなニセアカシ
アが植わっていたが、ある日電線に触るという理由でか
なりのニセアカシアが根元から伐採された。
隣家の大き
な松は塀を乗り越えて私たちの住む長屋の上に枝を広げ
ていた。私たちはその松が大きな慰めであった。
家主は
屋根に葉が落ちて困ると隣家に松を切ることを申し人れ
た。
どんな立派な神殿でもそこに生える松ほどの価値も
無い、私たちは人の身勝手に悲しみを越えて怒りを持っ
た。
私
が一時通った大学の駅前に雑居店舗があって、その
中にパン屋があった。妻はよくそこへバンの耳を貰いに
ゆきそれが私たちの主食であった。
妻の母はみっともな
いと嘆き私を蔑み妻を罵った。妻にとっては苦痛であっ
たろうが、私にとってはそんなことは痛くも痒くもなか
った。妻の母はますます私を憎んだ。
私たちは若かった。
私たちは夢を食べて生きていたのだ。人の世の様々な愚
かしさを音楽や書物や絵を描くことで覆うことができた。
バッハは天上の調べを奏で、ドストエフスキーは人間の
愚昧に虐げられた人々の光明を知らしめ、ピカソは自然
に匹敵する人の想像力を具現した。
パ
ン屋のおばさんは美人ではないが通常とは違う愛ら
しさがあった。妻がパンの耳を賛いに行くと、亭主の眼
を盗みフカフカのパンをサッと耳パンの中に入れ素早く
包み、どうもありがとうございますと譬えようもない笑
みを浮かべてそれを妻に手渡すのであった。施しを与え
るという感は全く無い、天性の善良さであった。今もお
ばさんの顔は鮮明である。
人は一生を生きてもこの様な
顔に出会すことは希であろうし気付くことも無いであろ
う。真のカとは人に気付かれることもなく人の魂に分け
入り影響を与えるものである。
そしてそれは船やジェッ
ト機や電波などに頼ること無く世界の隅々に伝播する。
この世が末だ尚且つ消滅せずに在るのは、世に理もれた
この様な僅かな人たちがいるからなのだ。この僅かな人
たちがこの愚昧なる人の世を一身に背負っている。
私
はこの様な顔をもう一人知っている。
私が7、8歳の頃、父母と姉兄5人は二軒長屋の一方
に住んでいた。一方には末娘は私と同い年であるが上の
子たちは皆大きく、子沢山の家族が住んでいた。
この家
族がいつ隣に住むようになったのか覚えがない。時々そ
の隣の玄関から、松葉杖を突いたお兄さんが出てくるの
を目にするようになった。
帯を締めて浴衣の様な時も
あったが、大概は詰め襟の学生服であったから高校生
だったかも知れない。
私を含め悪童共が5、6人、さて
次はどんな悪さをしようかと考えあぐねていると、我が
家のお隣りさんの玄関が開いてその松葉杖のお兄さんが
出て来た。一瞬にして事は決った。
1人がサッと走り寄
り片足がある方の杖を蹴り上げ逃走した。お兄さんは暫
くぐらっと揺れて次いでドサッと引っ繰り返ってしまっ
た。次に一人がその杖を思い切り蹴飛ばし逃走した。私
も慌てて物陰に身を潜め息を詰めてお兄さんを見守った。
お兄さんは肘で杖に這い寄り顔を歪めてやっと立ち直っ
た。そしてお兄さんの顔には笑みが浮んでいた。悔しそ
うな笑みでも悲しそうな笑みでもなく、どう言えばいい
のだろうか。
そ
の頃は本当に子供が多かった。上は中学生から下は
よちよち歩きの子までが一緒になって遊んでいた。缶蹴
リ遊びなどすると、動きの鈍い子はとっぷり日の暮れる
まで鬼の役をさせられ泣きべそを掻いていた。しかし遊
びの術は大きい子から小さい子に確実に引き継がれた。
例の悪童共が又何か企んでいると例のお兄さんが玄関か
ら出て来た。
今度は杖を蹴飛ばしたりはしなかった。お
兄さんの周りを大声を張り上げてピョンピョン飛び跳ね
出したのだ。一人は片足が無い方のズボンの裾を引っ
張ったりした。しかし又倒そうとしたのではなかった。
昔前の悪戯を悔んでいた。あの笑みは皆の胸に応えたの
だ。
お兄さんは腋に松葉杖をキュツと挟み、片方の手を
一人の悪童の頭に置いた。その悪童の目はくりくりとし
ていた。そしてその手は私の頭にあった。
その笑みと手
は本当に優しかった。母の優しさとは違っていた。それ
からは皆お兄さんが出て来るのを楽しみにした。出て来
れば周りを跳ね、頭を撫でて貫いたがった。
しかしお兄さんは出て来なくなった。亡くなったのだ。
子
供は健忘症である。悪童共はお兄さんのことをすっ
かり忘れて又遊び惚けた。きっとあの悪童共は今でも忘
れているだろう。私もすっかり忘れていた。
妻と一緒になった頃、
古本屋でメーテルリンクの「貧者の宝」とい
う文庫本を手にした。メーテルリンクといえば「青い
鳥」で有名であるが、私はそれしか知らずその本が珍し
く又安いので買って帰った。
その中の「よう逝する運命の子たち」を読んだ時、
まざまざとお兄さんが蘇った。
この書を読まなかったら今でもお兄さんのことを忘れてい
たかも知れない。よう逝する運命の子たちはその運命の下
に人の数倍の早さで人生を生きる。お兄さんを思い出さ
なくてもそれはそれで構わない。お兄さんの魂は悪童共
の魂にしっかりと喰い込んでいる。今在る私の魂の半分
はお兄さんの魂だ。
私は恵まれた人間だ。
船
は急に進路を変えた。大きな入り江に入り汽笛を2
度鳴らした。
低い黒い瓦屋根が固まり、小さな桟橋には
人が群れている。揺れるのが好きなこの船もおとなしく
なった。桟橋の人たちは皆ニコニコして騒がしく、手作
業で荷降しが始まった。
皆見知らぬ人たちばかりでさて
どうしたものやら私はスタスタ歩き出した。集落の中を
どう通ったのか今では思い出せない。
湾を右手に勾配の
強い砂利道を歩いていた。道の両側は白い大きな芙蓉の
花が満開で、大樹が海を背景に大仰に枝を伸ばし、葉は
黒々と金色に輝いている。少し登ると小学校があった。
湾を見下す校庭は大きな松に囲われ、可愛いい木造校舎
は数段高いところにあって花壇には色とりどりの花が咲
いていた。
私の子供たちをこの学校に通わせたいな。
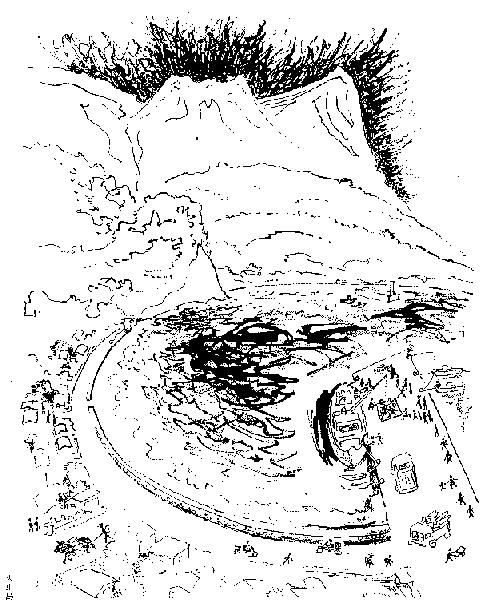
小
一時間歩いただろうか、丘を過ぎ海辺で道は途切れ
ていた。集落に戻って来ると四角い杭に口永良部出張所
とあった。小さなくすんだ木造家屋に入ると、細長いカ
ウンターの向うに頭の禿げた男性がポツネンと腰掛けて
いた。
今日は---この島には空家がありますでしょうか---、
禿げて眼の小さい日焼けした細長い顔のその人は
暫くポカンと私を眺めていた。
それから思い出したよう
に横にある白紙を取って何やら書き出した。カウンター
越しに覗くと、どうやら地図らしい。差し出された紙は
15件ほどの空家の地図であった。
宿を教えて貰い、礼を述べてそこを出た。
港
のある集落は本村といい瓢箪のちょうど括れた処
に当たり、南に面した平坦地でおよそ7、80戸が固
まっていた。その奥は水田が不規則な細い畦で区切られ
美しい景観を見せている。
翌目、地図を頼りに数件空屋
を見て廻り次の空屋に向かった。浅い谷間のコンクリー
トで固められた小道を少し登り、それが途切れた処に石
垣と竹で囲われた空屋があった。その石垣の中程に石段
があり、それが敷地の入り口であった。両側は大きなガ
ジュマルが生え、石段を登ると小さな庭につづいて土間
があった。そこで私はくるっと振り返えると、入り口の
ガジュマルの枝が互いに交叉してアーチになっており、
その中にまるで絵葉書さながらに火山が納まっていた。
私たちの住む家はここだ!と思った。
家 主はまだ三十歳代の漁師であった。この家を措りた いと申し出るとよかどと言う。家賃は幾らかと専ねると よかどと言う。家主は何かいろいろ私に言ったがほとん ど何のことか分からなかった。とにかく貸して呉れるよ うだ。私は住所氏名を紙に書いて渡し、すぐに引っ越し て来ると伝えて辞去した。
島
を後にしたその夜、火山が噴火した。
東京に戻って新聞でそのことを知ったのだが
妻はその噴火を、私たちが島に移り住むことを歓迎して
いると解釈したのである。
